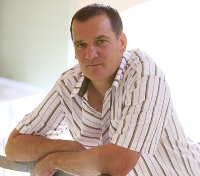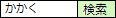
|
ドメーヌ・タンピエ、 バンドール
Domeine
Tampier. 2011 &
2012
& 2013 Bandol
- 産地 : フランス、バンドールAC
生産者 : ドメーヌ・タンピエ(ペイロー家)
醸造責任者・支配人 : ダニエル・ラヴィエ氏
畑 : プティ・ムーラン・ド・ラ・カディエールの区画と、ラ・バスティッドの区画で栽培された葡萄
ブドウ品種 :
ムールヴェドル70〜75%、グルナッシュ14〜16%、サンソー8〜9%、カリニャン0〜2%
※ヴィンテージに応じてアッサンブラージュの比率が若干異なる
単位収量 : 平均30〜38hl/ha
醸造・熟成 : 葡萄は全て手摘みで収穫され,選果台を使って傷んだ葡萄や未成熟な葡萄は全て取り除かれる。完全に除梗し,野性酵母のみを用いて発酵を行う。発酵は温度管理機能付きのステンレスタンクとセメントタンクで行われ、その後、フランス産オークの樽(容量25〜75ヘクトリットルまで様々な容量の樽を使用)に移し、マロラクティック発酵と熟成を行う。熟成期間は18〜20ヵ月。無清澄・無濾過で瓶詰め。
年間生産量 : 本
アルコール度 : 13.0度
タイプ : 赤ワイン。フルボディ。
 : ビオデナミ : ビオデナミ
強烈なルビーレッドの色調。ブラック・フルーツを思わせる香りがあり、とても良くバランス取れた味わい。タンニンは顕著だが、すべてがまろやか。5〜6年の熟成とともに皮や動物、下草、小さなレッドフルーツなどの香りを発散するようになる。瓶詰めから3〜4年以内に心地良く味わうことができるが、ワインのバランスの良さから15年か、それ以上の熟成も可能。
 
|
- ドメーヌの異なる区画で栽培された葡萄のアッサンブラージュから生まれる赤のスタンダード・キュヴェ。
ヴィンテージに応じて若干比率は異なるが、ムールヴェードルを主体にグルナッシュとサンソー、そしてごく僅かに古木のカリニャン(2%)が加えられる。
また、主としてPetit Moulin de la
Cadiereプティ・ムーラン・ド・ラ・カディエールの区画と、ラ・バスティッドの区画で栽培された葡萄がアッサンブラージュされる。
プティ・ムーラン・ド・ラ・カディエールは、南に面した起伏のある棚田状の畑。ルディステスと呼ばれる中世代の厚歯二枚貝の石灰質の土壌であることが特徴。
ラ・バスティッドは、ドメーヌの建物の周りにある区画で、固く、心土まで続く粘土質の土壌が多くみられるが、所々流砂層や泥灰砂質の土壌が見受けられる。この部分がワインにもたらす役目はあまり大きくないと思われがちだ、非常に水捌けが良く,過剰な豊満さではなく、多くのフィネスをワインに付与してくれる特徴がある。
-
- 「レ・メイユール・ヴァン・ド・フランス2010年版」ではピバルノンに勝ち,トレヴァロンと同じ17/20点評価。ワイン・アドヴォケイトの2005年物水平試飲では,他のドメーヌのバンドールが80点台に低迷する中,スタンダード・キュヴェとして見事パーカーポイント90点を獲得し,群を抜く評価を獲得した実績を持つ。
-
|
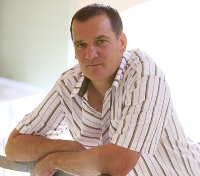
現支配人ダニエル・ラヴィエ

中興の祖
ジャン=マリーとフランソワの兄弟
|
|
バンドール赤に使われる葡萄が栽培されるドメーヌの建物の周りのラ・バスティッドの区画
|

|

|
|
バンドール赤に使われる葡萄が栽培されるプティ・ムーラン・ド・ラ・カディエールの区画
|

|

|
|
|
■□■□ ドメーヌ・タンピエ □■□■
|

|
かつてドメーヌ・タンピエで研鑽を積んだブルゴーニュのスーパー・ネゴシアン“ヴェルジェ”のジャン=マリー・ギュファンスが,「私に最も感銘を与え,現在のワイン造りに影響を及ぼしたのはリュシアン・ペイローである」と述べているように,ドメーヌ・タンピエは,原産地統制呼称「バンドール」の創設者であり,バンドールの父と呼ばれたドメーヌの創設者リュシアン・ペイロー/Lucien
Peyraud,そしてリュシアンの後を継いだ2人の息子,ジャン=マリーとフランソワの兄弟によって,名声と栄光を欲しいまましてきました。しかし,その伝説的ドメーヌも90年代の一時期にかつての勢いを失い,加えて2000年にはジャン=マリーとフランソワ兄弟が引退。バンドールの旗手たるドメーヌの未来は風前の灯かと思われました。
|
- その危機を救ったのが,現在ドメーヌの支配人兼醸造家を務めるダニエル・ラヴィエ/Daniel
Ravierです。ドメーヌ・オットを皮切りに南仏で10年近く働いてきたダニエル・ラヴィエは,未来を嘱望される天才醸造家。その証拠に,毎年フランスの各アペラシオンから1人ずつ若き才能を選出している『ルヴュ・デュ・ヴァン・ド・フランス』はダニエル・ラヴィエを2004年度の《若き才能》に選出。続いて,2005年版の『ゴー・ミヨ(ワイン・ガイド)』では,見事,トップの四つ星ドメーヌに返り咲きを果たしました。また,『ル・クラスマン(現メイユール・デ・ヴァン・ド・フランス)2007年版』においては,ロバート・パーカーに<生涯最高の発見!>と言わしめたドメーヌ・ド・トレヴァロンと並び,プロヴァンスのドメーヌとしては最高峰の二つ星に格付けされたのです。
|
|
バイオダイナミックス農法へ 歴史的ドメーヌのさらなる進化
- ドメーヌ・タンピエの所有する畑の面積は併せると30ha近くに及び、内、55%にはムールヴェードルが、23%にはサンソーが、20%にはグルナッシュが、そして少量のシラー、カリニャン、クレーレット、マルサンヌ、ユニ・ブランが植えられています。
- この畑で育まれたブドウ果を用い、栽培、醸造、瓶詰めに至るまで全てを手掛ける古くからの伝統を今でも忠実に重んじているドメーヌ・タンピエは、近代的な水撒き用のスプリンクラーや農薬(暑く乾燥したミクロクリマの恩恵に浴しているため、ウドンコ病やオイディウム菌の害を被ることはもともと稀)、酸化を防ぐための二酸化硫黄を使用していません(ムールヴェードルは酸化に対して非常に抵抗力があるので、この品種の比率を高くすることで二酸化硫黄の不使用が可能となった)。
- また、「ブドウ樹の根は、土中の自然物質のみから養分を吸い取る。人工的な物質を用いることは、土中の微生物の生態系リズムを崩し、そのままワインの味わいに悪影響を及ぼしてしまう。」という考えに基づいているので、今では一般化されている化学肥料の代わりに発酵後のブドウ果の絞り滓を肥料として土中に混ぜるなど、1980年代より独自の有機農法を行い、テロワールの特質を備えたワインを造り出しています。
- さらにドメーヌ・タンピエでは、1990年代中期より新たにバイオダイナミックス農法の手法を採り入れるようになりました。例えば、ブドウ樹の剪定やワインの瓶詰めは、「月の満ち欠け」のリズムに準じ、月が欠けて行く期間(満月から新月になる14日間)に限定して行っています。この時期は大気圧が高まり、樽やタンク中のワイン、あるいはブドウ樹中を流れる樹液が安定した状態にあるからです。これによって剪定を行ってもブドウ樹は腐ることなく樹齢を重ねることが出来、瓶詰めではボトル・ショックに陥るリスクを最小限に抑え、よりよい瓶内熟成が得られるといった利点があります。ドメーヌ・タンピエは、今後数年の間に完全なバイオダイナミックス農法へ移行することも示唆しています。
- また、このドメーヌの特徴として、もうひとつ挙げられるのは、アッサンブラージュを発酵の段階で行っていることです。ジャン=マリーは、「これは私達の長年培われてきた経験の上で判断したことですが、品種ごとに各々発酵させた後にアッサンブラージュさせたものよりも、発酵前の段階でアッサンブラージュさせた方が、より調和のとれた個性的なワインが仕上がると考えているからです。」と語ります。
- このようにジャン=マリーとフランソワは、バンドールのトップ・ドメーヌとしての伝統と、バンドールの父と呼ばれてきた亡きリュシアン・ペイローの威光に安住することなく、さらなる至高を目指しているのです。
(以上、インポーター・リリースシートより)
|
|